【連携する研究者たち】 自然界で見つけた化学成分を医薬品につなげる研究リレー
物質生命科学科
桐原正之 教授
鎌田昂 准教授
小土橋陽平 准教授
桐原正之 教授
鎌田昂 准教授
小土橋陽平 准教授

静岡理工科大学では教員同士の共同研究を推進しています。一つの専門分野にとどまっていた成果が別の分野を刺激して、さらに大きな成果へと広がっていく可能性があるからです。今回は、海洋生物やコケ類から見つけた薬剤になりうる有機化合物をきっかけに、人工的な合成や、医薬品の投与システムにまで挑戦する、物質生命科学科の桐原正之教授、小土橋陽平准教授、鎌田昂准教授の3人の研究を紹介します(以下、発言者のお名前は敬称略、聞き手は物質生命科学科 山﨑誠志教授)。

物質生命科学科 鎌田昂 准教授
――まず、今回の連携研究できっかけ役となる鎌田先生からお話を聞かせて下さい。
鎌田 私は海洋生物やコケ類、生薬植物などから有用な化学物質を見つけ出し、医薬品、抗菌剤、抗カビ剤そして塗料として応用する研究をしています。例えば、ソゾという海藻は他の生物に食べられないように塩素や臭素を含む有機化合物(天然有機化合物)を生成します。こうした化合物のなかにはフジツボなどが付着しにくかったり、抗がん剤として開発が期待されたりする成分が見つかっています。
商品や医薬品にするときに、これらをすべて自然界から取り出すことは現実的ではありません。そこで、有機合成化学の専門家である桐原先生に、そうした天然有機化合物と同様の化合物を人工的に合成してもらおうと考えています。
桐原 鎌田先生は、塩素や臭素などハロゲン(※1)を含む天然有機化合物を数多く扱っています。これらが船底用塗料や医薬品の基になる可能性があるわけですが、一方、私の研究テーマにハロゲンを含む有機化合物の合成があります。つまり、鎌田先生の成果は研究テーマとして引き継ぎやすい、非常にフィットしたテーマなのです。合成の手法としては環境にやさしい有機合成反応(※2)を採用したいと思っています。これも私どもの研究室のテーマの一つです。
※1 ハロゲン:フッ素(F)、塩素(Cl)、臭素(Br)、ヨウ素(I)などの総称。周期表で最も右側の列は希ガスだが、ハロゲンはその一つ左側の列を占める。
※2 環境にやさしい有機合成反応:有害な試薬を使ったり危険な廃棄物を出したりすることのない合成反応。詳しくは桐原研究室のページへ
鎌田 私は海洋生物やコケ類、生薬植物などから有用な化学物質を見つけ出し、医薬品、抗菌剤、抗カビ剤そして塗料として応用する研究をしています。例えば、ソゾという海藻は他の生物に食べられないように塩素や臭素を含む有機化合物(天然有機化合物)を生成します。こうした化合物のなかにはフジツボなどが付着しにくかったり、抗がん剤として開発が期待されたりする成分が見つかっています。
商品や医薬品にするときに、これらをすべて自然界から取り出すことは現実的ではありません。そこで、有機合成化学の専門家である桐原先生に、そうした天然有機化合物と同様の化合物を人工的に合成してもらおうと考えています。
桐原 鎌田先生は、塩素や臭素などハロゲン(※1)を含む天然有機化合物を数多く扱っています。これらが船底用塗料や医薬品の基になる可能性があるわけですが、一方、私の研究テーマにハロゲンを含む有機化合物の合成があります。つまり、鎌田先生の成果は研究テーマとして引き継ぎやすい、非常にフィットしたテーマなのです。合成の手法としては環境にやさしい有機合成反応(※2)を採用したいと思っています。これも私どもの研究室のテーマの一つです。
※1 ハロゲン:フッ素(F)、塩素(Cl)、臭素(Br)、ヨウ素(I)などの総称。周期表で最も右側の列は希ガスだが、ハロゲンはその一つ左側の列を占める。
※2 環境にやさしい有機合成反応:有害な試薬を使ったり危険な廃棄物を出したりすることのない合成反応。詳しくは桐原研究室のページへ

物質生命科学科 桐原正之 教授
また、鎌田先生が見つけてくる天然有機化合物の一部を別の元素に置き換える、例えば塩素や臭素をフッ素に置き換えることで特性が変わる可能性がある。期待していた特性に近づく可能性もあるわけです。
こうした連携研究の中から、抗がん剤のような薬剤を開発していこうとしています。
ーー船底用塗料や医薬品への効果が確認され、化学的に大量合成できれば、次は小土橋先生の出番ですね。
小土橋 はい、その通りです。私の専門は高分子化学で、ドラッグデリバリーシステム(DDS)に興味があります。研究テーマのひとつとして、薬剤をナノメートルサイズのカプセル(ナノカプセル)に入れて運び、がん細胞など患部に着いたら薬剤を放出するシステムを開発しています。効率が良いだけでなく、副作用を最大限に抑えられます。
桐原先生と鎌田先生の研究から薬剤が出来たら、それを運ぶ最適なナノカプセルを設計・開発したいと思っています。私が考えているのは次世代のカプセルです。今のカプセルはどんな薬剤にも同じようなカプセルを使っているのですが、そうではなくて、その薬剤が最も効果を発揮する場所に、最も効果を発揮するタイミングで、適切な量を提供する専用のカプセルです。薬剤それぞれの性質に合わせた専用のカプセルにすることで、さらに薬効を上げることができるだろうと考えます。
――成果を引き継ぐ見事なバトンリレーの体制が整いましたね。物質生命科学科では薬剤以外にも研究の連携を進めているようですが、他の先生と連携したり、静岡理工科大学の学生たちと関わったりする中で刺激を受けたことや心がけていることはありますか?研究以外のことでもかまいません。
こうした連携研究の中から、抗がん剤のような薬剤を開発していこうとしています。
ーー船底用塗料や医薬品への効果が確認され、化学的に大量合成できれば、次は小土橋先生の出番ですね。
小土橋 はい、その通りです。私の専門は高分子化学で、ドラッグデリバリーシステム(DDS)に興味があります。研究テーマのひとつとして、薬剤をナノメートルサイズのカプセル(ナノカプセル)に入れて運び、がん細胞など患部に着いたら薬剤を放出するシステムを開発しています。効率が良いだけでなく、副作用を最大限に抑えられます。
桐原先生と鎌田先生の研究から薬剤が出来たら、それを運ぶ最適なナノカプセルを設計・開発したいと思っています。私が考えているのは次世代のカプセルです。今のカプセルはどんな薬剤にも同じようなカプセルを使っているのですが、そうではなくて、その薬剤が最も効果を発揮する場所に、最も効果を発揮するタイミングで、適切な量を提供する専用のカプセルです。薬剤それぞれの性質に合わせた専用のカプセルにすることで、さらに薬効を上げることができるだろうと考えます。
――成果を引き継ぐ見事なバトンリレーの体制が整いましたね。物質生命科学科では薬剤以外にも研究の連携を進めているようですが、他の先生と連携したり、静岡理工科大学の学生たちと関わったりする中で刺激を受けたことや心がけていることはありますか?研究以外のことでもかまいません。
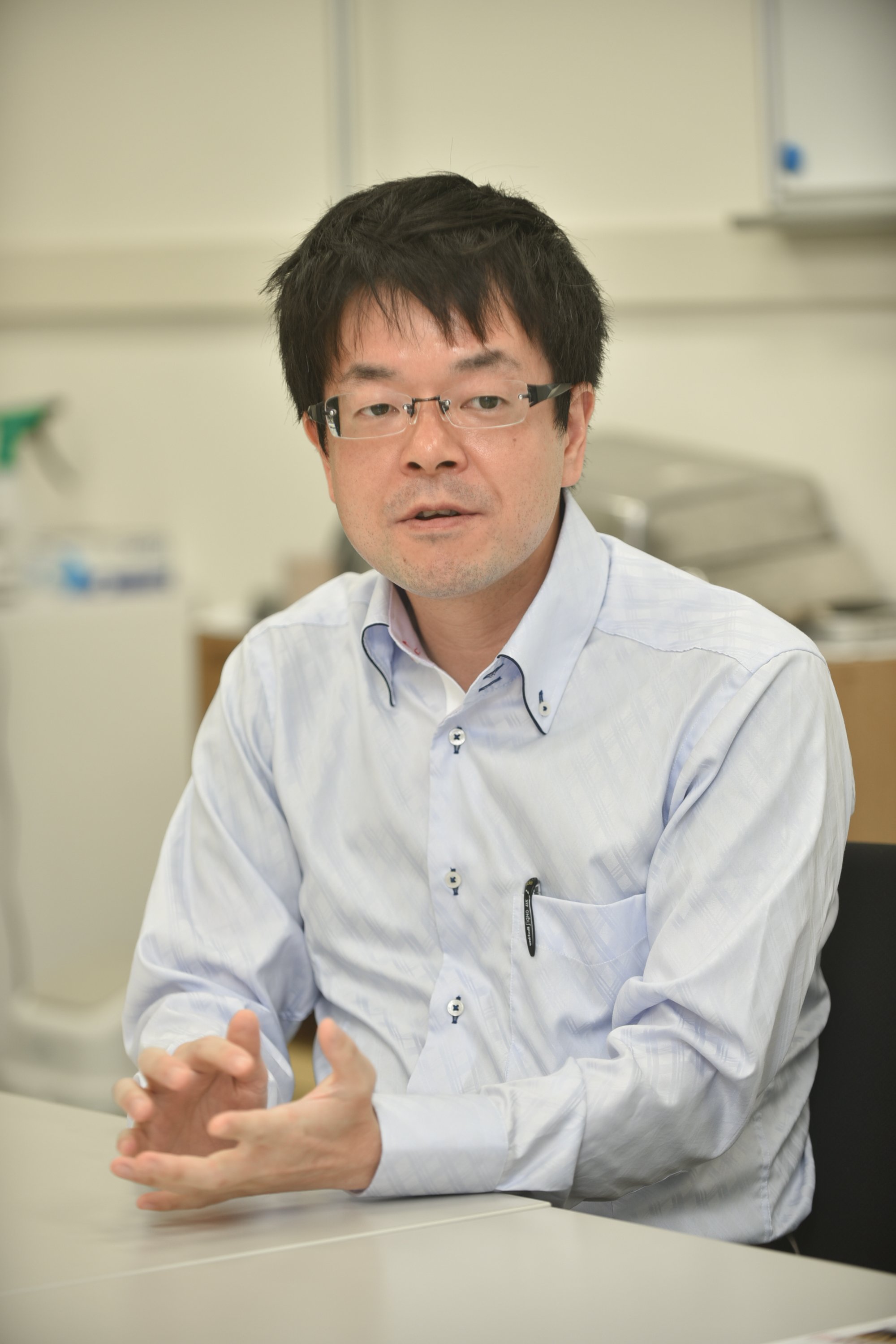
物質生命科学科 小土橋陽平 准教授
小土橋 現在、私の研究室に、抗菌性ポリマーの研究を中心になって進めている修士1年の学生がいます。実は彼は学部4年のときに桐原研究室にいた学生なのです。桐原先生と共同研究を進めていたところ、高分子化合物に興味を持ち、大学院から私の研究室に来てくれました。とてもアクティブで、本学の応用微生物学研究室(齋藤明広 教授)や他大学の医学部とも共同研究を行っています。分野横断型の共同研究を進めたことで学生たちの視野が広がり、興味の幅や研究の幅も広がったようです。
鎌田 私の研究室では野外活動と実験化学の融合に重きを置いています。先日は、研究室配属の前年から天然物化学に興味をもってくれた釣り好きの3年生たちと浜名湖のアメフラシを採集してきました。他に、伊豆半島の最南端にあたる下田へ海藻の調査・採集にも行ってきました。こうした野外活動を通じて得た発想が後に実験化学で活きるのです。採集したサンプルから得た化合物の構造決定には核磁気共鳴装置(NMR)を利用するのですが、構造解析にはパズルと似た楽しさがあります。数学や物理が苦手な学生でも、パズルゲームが得意な学生は好きになると思います。
——このように研究手法の異なる研究室が横連携すると、学生にとっては刺激的ですよね。静岡理工科大学の学生は実験好きな人が多いので、その好きの幅も広がるでしょう。構造解析から入って化学合成に興味を持ってもいいし、高分子化学からフィールドワークに移るのもありだと思います。
鎌田 私の研究室では野外活動と実験化学の融合に重きを置いています。先日は、研究室配属の前年から天然物化学に興味をもってくれた釣り好きの3年生たちと浜名湖のアメフラシを採集してきました。他に、伊豆半島の最南端にあたる下田へ海藻の調査・採集にも行ってきました。こうした野外活動を通じて得た発想が後に実験化学で活きるのです。採集したサンプルから得た化合物の構造決定には核磁気共鳴装置(NMR)を利用するのですが、構造解析にはパズルと似た楽しさがあります。数学や物理が苦手な学生でも、パズルゲームが得意な学生は好きになると思います。
——このように研究手法の異なる研究室が横連携すると、学生にとっては刺激的ですよね。静岡理工科大学の学生は実験好きな人が多いので、その好きの幅も広がるでしょう。構造解析から入って化学合成に興味を持ってもいいし、高分子化学からフィールドワークに移るのもありだと思います。

聞き手の山﨑誠志教授
桐原 そうですね、学生たちの環境にもいい影響を与えていると思います。私は普段から、学生には日々楽しくワクワク感をもって研究してもらおうと心がけています。そうした研究から何かを発見したとか製品開発に協力したといった経験につながればさらにうれしいですし、そんな環境から巣立った卒業生の中から世の中を変えるようなインパクトのある仕事をする人が現れたら素晴らしいですよね。
研究者プロフィール
桐原正之 教授・鎌田昂 准教授・小土橋陽平 准教授
物質生命科学科
桐原正之 教授
1990年 大阪大学大学院薬学研究科博士後期課程修了
1993年 富山医科薬科大学 助手(薬学部)
2001年 静岡理工科大学 准教授(理工学部)
2012年 現職
小土橋陽平 教授
2011年 鹿児島大学大学院 理工学研究科 博士課程修了
2011年 アルバータ大学 化学/物質工学科 博士研究員
2013年 物質・材料研究機構(NIMS) WPI-MANA ICYS研究員
2016年 現職
鎌田昂 教授
2013年 マレーシア国立サバ大学大学院 博士課程修了
2014年 サバ大学 熱帯生物保全研究所 シニア講師
2018年 現職
物質生命科学科
桐原正之 教授
1990年 大阪大学大学院薬学研究科博士後期課程修了
1993年 富山医科薬科大学 助手(薬学部)
2001年 静岡理工科大学 准教授(理工学部)
2012年 現職
小土橋陽平 教授
2011年 鹿児島大学大学院 理工学研究科 博士課程修了
2011年 アルバータ大学 化学/物質工学科 博士研究員
2013年 物質・材料研究機構(NIMS) WPI-MANA ICYS研究員
2016年 現職
鎌田昂 教授
2013年 マレーシア国立サバ大学大学院 博士課程修了
2014年 サバ大学 熱帯生物保全研究所 シニア講師
2018年 現職

