実践に裏打ちされた「仕事の進め方」理論
情報デザイン学科
林章浩 教授
林章浩 教授
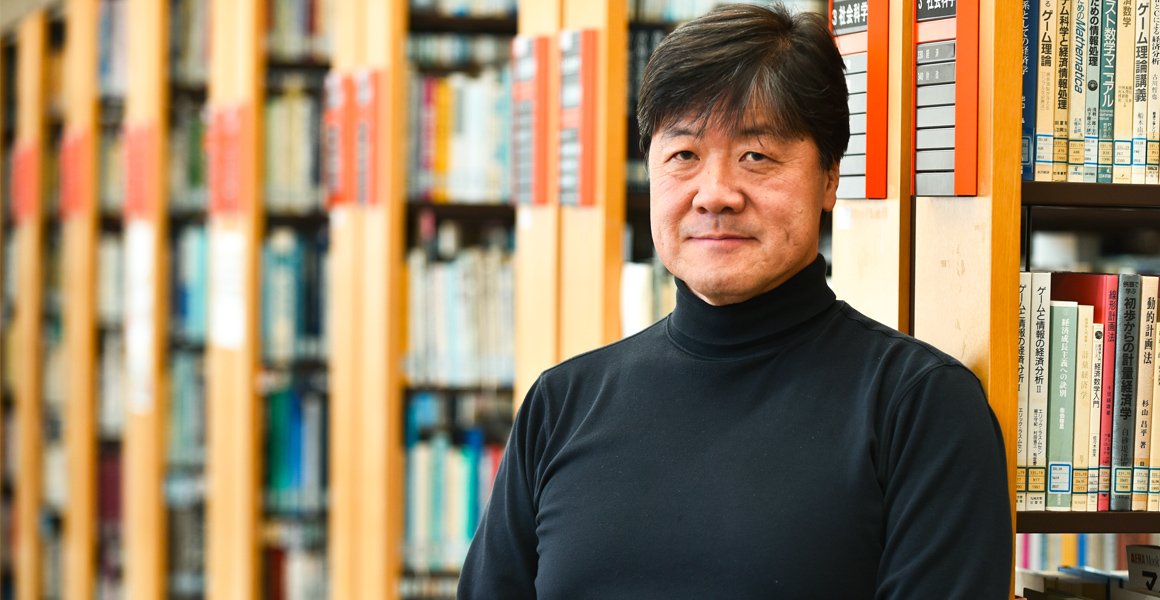
誰も失敗はしたくない。しかし仕事が失敗に終わることはある。納期に遅れてしまったり、求められる品質に届かなかったり・・・。こうした失敗をせずにうまく仕事を進める方法はないものでしょうか。
失敗しない仕事の進め方は、これまでにいくつも方法論が提案されてきました。現在、世界で最も広く知られているのはプロジェクト管理という概念でしょう。仕事(プロジェクト)の立ち上げから終了までを複数のプロセスとして捉えること、PDCAサイクル(※1)と呼ばれる管理サイクルを回すことなどが特徴の手法です。「ああ、あれか」と思い当たる人は多いかもしれません。
※1 PDCAサイクル:業務を進める際に、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)を繰り返し、継続的に業務改善を進める手法
情報デザイン学科の林章浩教授は、プロジェクト管理のプロフェッショナルです。ソフトウエア開発に関連した資格を中心に、CMMリードアセッサ(※2)、CMMIリードアセッサ(※3)、ISO/IEC 15504リードアセッサ(※4)など、いくつもの資格を取得しています。
※2 CMMリードアセッサ:CMMはCapability Maturity Modelの略。日本語では「能力成熟度モデル」。外部の業者や組織にソフトウエア開発を委託する際に、その業者・組織がどの程度のプロセス管理能力を有しているかを5段階の成熟度で評価するモデル。発注前に業者・組織を評価できるため、ソフトウエア開発が失敗するリスクを減らせる。このモデルに従い業者・組織を診断・評価する人をアセッサといい、さらに高度な診断・評価ができる人をリードアセッサという
※3 CMMIリードアセッサ:前述のCMMはソフトウエア開発を対象としたモデルであるが、同様にシステムエンジニアリングやシステム調達などを対象に、複数のモデルが開発された。これらモデルを統合したものがCMMI(Capability Maturity Model Integration)である。日本語では「能力成熟度モデル統合」。CMMIリードアセッサは高度なCMMI診断・評価ができる人のこと
※4 ISO/IEC 15504:CMMやISO9001(品質マネジメントシステムに関する規格)など多くの評価モデルを参考に、これらの共通部分を規定した枠組み。国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)の合同技術委員会が策定した
失敗しない仕事の進め方は、これまでにいくつも方法論が提案されてきました。現在、世界で最も広く知られているのはプロジェクト管理という概念でしょう。仕事(プロジェクト)の立ち上げから終了までを複数のプロセスとして捉えること、PDCAサイクル(※1)と呼ばれる管理サイクルを回すことなどが特徴の手法です。「ああ、あれか」と思い当たる人は多いかもしれません。
※1 PDCAサイクル:業務を進める際に、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)を繰り返し、継続的に業務改善を進める手法
情報デザイン学科の林章浩教授は、プロジェクト管理のプロフェッショナルです。ソフトウエア開発に関連した資格を中心に、CMMリードアセッサ(※2)、CMMIリードアセッサ(※3)、ISO/IEC 15504リードアセッサ(※4)など、いくつもの資格を取得しています。
※2 CMMリードアセッサ:CMMはCapability Maturity Modelの略。日本語では「能力成熟度モデル」。外部の業者や組織にソフトウエア開発を委託する際に、その業者・組織がどの程度のプロセス管理能力を有しているかを5段階の成熟度で評価するモデル。発注前に業者・組織を評価できるため、ソフトウエア開発が失敗するリスクを減らせる。このモデルに従い業者・組織を診断・評価する人をアセッサといい、さらに高度な診断・評価ができる人をリードアセッサという
※3 CMMIリードアセッサ:前述のCMMはソフトウエア開発を対象としたモデルであるが、同様にシステムエンジニアリングやシステム調達などを対象に、複数のモデルが開発された。これらモデルを統合したものがCMMI(Capability Maturity Model Integration)である。日本語では「能力成熟度モデル統合」。CMMIリードアセッサは高度なCMMI診断・評価ができる人のこと
※4 ISO/IEC 15504:CMMやISO9001(品質マネジメントシステムに関する規格)など多くの評価モデルを参考に、これらの共通部分を規定した枠組み。国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)の合同技術委員会が策定した
失敗できない国際会議
理論に長けているだけでありません。林教授は、米モトローラ、NTTグループ、日本IBMといった世界に名だたる企業でプロジェクト管理やソフトウエアの品質管理といった実務を長く経験してきました。理論と経験の両面からプロジェクト管理という“教養”を身に付けているのです。
例えば、1999年に開催された国際コンピュータ通信会議1999(ICCC'99)(※5)では運営の取り仕切りの一端を担いました。英語で行われる世界最大級のこの国際会議は、日本の運営力が試される会議でした。海外からはノーベル物理学賞受賞者のアーノ・ペンジアス氏(ルーセント・テクノロジー ベル研究所)や、サンマイクロシステムズ社のチーフサイエンティストであるビル・ジョイ(ウィリアム・ネルソン・ジョイ)氏などを招きます。対して国内からは野田聖子郵政大臣があいさつに立ち、日本電信電話の宮津純一郎社長、ソニーの出井伸之社長、そして石田晴久教授や村井純教授など情報系の研究者がキーノート講演を務める、いわばオールジャパンで取り組んだ会議でした(所属や肩書きはいずれも当時のもの)。会場は東京国際フォーラム、来場者は千人規模。失敗するわけにはいきません。
※5 国際コンピュータ通信会議(ICCC):ICCCはInternational Conference on Computer Communicationの略。1999年に東京で開催されたICCCは14回目にあたる
例えば、1999年に開催された国際コンピュータ通信会議1999(ICCC'99)(※5)では運営の取り仕切りの一端を担いました。英語で行われる世界最大級のこの国際会議は、日本の運営力が試される会議でした。海外からはノーベル物理学賞受賞者のアーノ・ペンジアス氏(ルーセント・テクノロジー ベル研究所)や、サンマイクロシステムズ社のチーフサイエンティストであるビル・ジョイ(ウィリアム・ネルソン・ジョイ)氏などを招きます。対して国内からは野田聖子郵政大臣があいさつに立ち、日本電信電話の宮津純一郎社長、ソニーの出井伸之社長、そして石田晴久教授や村井純教授など情報系の研究者がキーノート講演を務める、いわばオールジャパンで取り組んだ会議でした(所属や肩書きはいずれも当時のもの)。会場は東京国際フォーラム、来場者は千人規模。失敗するわけにはいきません。
※5 国際コンピュータ通信会議(ICCC):ICCCはInternational Conference on Computer Communicationの略。1999年に東京で開催されたICCCは14回目にあたる

車いす移動ロボットの試作機
準備は開催の2年前から始めましたが、課題やトラブルはいくつもありした。例えば著名人のスケジュールは早めに押さえなくてはいけません。最も早くにスケジュールを確保すべき一人が郵政大臣でしたが、準備期間の途中で橋本内閣から小渕内閣へ代わるハプニングがありました。当然、郵政大臣も代わります。それでも無事に小渕内閣の郵政大臣、野田聖子氏のスケジュールを確保しました。また、これだけ大規模ですと費用もかかります。その費用は民間から寄付を募ることに決め、出してもらえる企業探しに奔走しました。
こうした作業を洗い出し、リスク抽出を行い、複数の作業(プロセス)を並行して進めながら、管理を徹底することで会議を成功裏に終わらせました。日本ではこの会議の後、インターネットが一気に広まりました。新時代を開く意義のある会議となったのです。
日本IBM在籍中には、企業からプロセス改善やプロジェクト管理のコンサルティングを委託されました。手がけた10数件の案件のなかには数年がかりのプロジェクトもありました。
こうした作業を洗い出し、リスク抽出を行い、複数の作業(プロセス)を並行して進めながら、管理を徹底することで会議を成功裏に終わらせました。日本ではこの会議の後、インターネットが一気に広まりました。新時代を開く意義のある会議となったのです。
日本IBM在籍中には、企業からプロセス改善やプロジェクト管理のコンサルティングを委託されました。手がけた10数件の案件のなかには数年がかりのプロジェクトもありました。
改善の気づきを地域企業に
プロジェクト管理と聞くと大規模な情報系のプロジェクトに適用する特別な手法のように感じるかもしれません。しかし林教授は「どんな企業の仕事でもプロジェクトと考えることができる」と言います。
計画書を作り、計画通りの品質を確保し、最後まで遂行するという流れがあれば、その流れはプロジェクトとして捉えることができ、適切に管理することができる。それが広い意味でのプロジェクト管理です。
仕事の進め方にはさまざまな方法がありますが、林教授が薦める方法は「ベストプラクティス」と呼ばれているものです。ベストプラクティスとは、ある結果を得るのに最も効率のよい技法、手法、プロセス、活動などを指します。このベストプラクティスと現状のギャップを認識して、自己流の技法やプロセスをあるべき技法やプロセスへ改善していきます。改善にあたっては、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)のサイクルを繰り返します。
「専門用語が出てきてピンと来ない」という人にはトヨタ生産方式の話をすることもあります。「5S、すなわち整理、整頓、清掃、清潔、躾(しつけ)の実践を考えてみましょう。5Sで業績が伸びるのならば、5Sを自社に取り入れる。その場合に、5Sと現状とのギャップを認識して、どのようにいつまでに対応するかを考えれば、それがプロジェクト管理の第一歩になるのです」(林教授)。
2018年に着任し、ようやく講義や研究に慣れてきた林教授ですが、今後、地域の企業とはどのような連携を考えているのでしょうか。「企業の皆さんを前にプロジェクト管理の講義をするのも一つの連携でしょう。ですが、聞いていただくだけではなかなか身に付くレベルにはなりません」。これも林教授の経験から得た実感です。実際に企業の中に入り、分析や実験をすることで、ようやく効果のあるプロセス改善につなげられることをコンサルティングの経験から知っているのです。講義や講演よりも深く踏み込むこと、とはいえ有料のコンサルティングと同じことをするのではなく、大学の研究や教育にとっても意義のある連携となること。そうした連携の形を探っている途中のようです。
林教授と地域のつながりが深まり、共同研究が広がっていけば、地域企業の仕事は高い確率で、失敗の少ない効率的な進め方になるはずです。「何を改善するか、企業の皆さんと一緒に考えていくことが地域の発展につながると思います」(林教授)。
計画書を作り、計画通りの品質を確保し、最後まで遂行するという流れがあれば、その流れはプロジェクトとして捉えることができ、適切に管理することができる。それが広い意味でのプロジェクト管理です。
仕事の進め方にはさまざまな方法がありますが、林教授が薦める方法は「ベストプラクティス」と呼ばれているものです。ベストプラクティスとは、ある結果を得るのに最も効率のよい技法、手法、プロセス、活動などを指します。このベストプラクティスと現状のギャップを認識して、自己流の技法やプロセスをあるべき技法やプロセスへ改善していきます。改善にあたっては、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)のサイクルを繰り返します。
「専門用語が出てきてピンと来ない」という人にはトヨタ生産方式の話をすることもあります。「5S、すなわち整理、整頓、清掃、清潔、躾(しつけ)の実践を考えてみましょう。5Sで業績が伸びるのならば、5Sを自社に取り入れる。その場合に、5Sと現状とのギャップを認識して、どのようにいつまでに対応するかを考えれば、それがプロジェクト管理の第一歩になるのです」(林教授)。
2018年に着任し、ようやく講義や研究に慣れてきた林教授ですが、今後、地域の企業とはどのような連携を考えているのでしょうか。「企業の皆さんを前にプロジェクト管理の講義をするのも一つの連携でしょう。ですが、聞いていただくだけではなかなか身に付くレベルにはなりません」。これも林教授の経験から得た実感です。実際に企業の中に入り、分析や実験をすることで、ようやく効果のあるプロセス改善につなげられることをコンサルティングの経験から知っているのです。講義や講演よりも深く踏み込むこと、とはいえ有料のコンサルティングと同じことをするのではなく、大学の研究や教育にとっても意義のある連携となること。そうした連携の形を探っている途中のようです。
林教授と地域のつながりが深まり、共同研究が広がっていけば、地域企業の仕事は高い確率で、失敗の少ない効率的な進め方になるはずです。「何を改善するか、企業の皆さんと一緒に考えていくことが地域の発展につながると思います」(林教授)。
研究者プロフィール
林章浩 教授
情報デザイン学科
博士(システムズ・マネジメント)
博士(ソフトウエア工学)
1992年 米モトローラ社ページンググループ ワールドヘッドクォータ
1993年 NTT本社、NTT研究所、NTTコミュニケーションズ、NTTデータなど、NTTグループ
に勤務
2006年 IBMビジネスコンサルティングサービス、日本IBM
2018年 現職
情報デザイン学科
博士(システムズ・マネジメント)
博士(ソフトウエア工学)
1992年 米モトローラ社ページンググループ ワールドヘッドクォータ
1993年 NTT本社、NTT研究所、NTTコミュニケーションズ、NTTデータなど、NTTグループ
に勤務
2006年 IBMビジネスコンサルティングサービス、日本IBM
2018年 現職

