進化する車に人の心は追いつくのか
情報デザイン学科
紀ノ定保礼 准教授
紀ノ定保礼 准教授

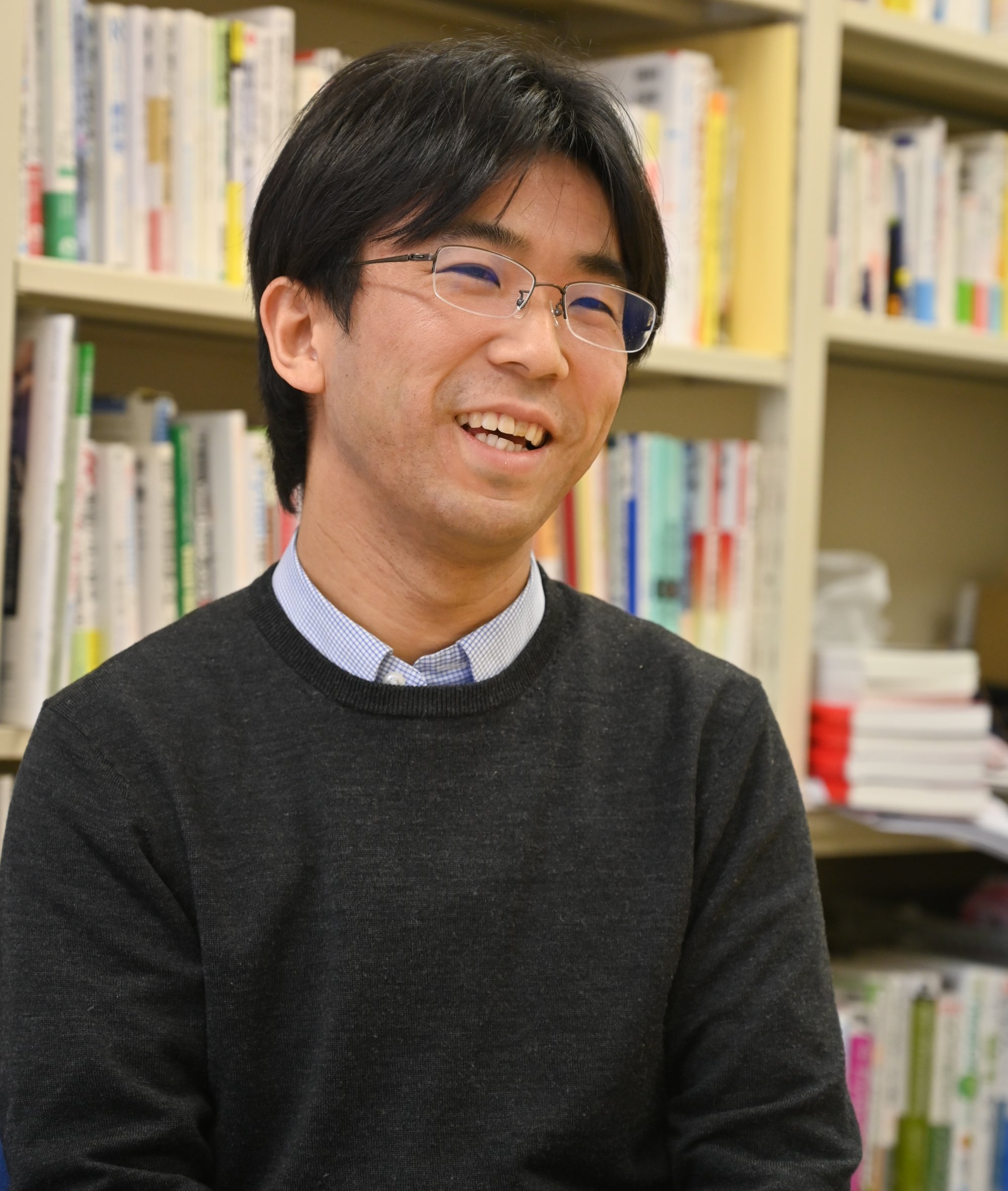
自動運転に向けて自動車(以下、車と表記)の技術が進み、運転の環境が大きく変わろうとしています。ドライバーや周囲にいる人たちは進化する車の恩恵を素直に受け取れるのでしょうか、それともどこか適応できない状況や思わぬストレスに戸惑うのでしょうか。
情報デザイン学科の紀ノ定保礼講師は人の認知に興味を持っています。特に、技術の進歩によって変わっていく環境のなかで、人はきちんと認識し対応できるのか、対応できないのであれば技術や社会にフィードバックすべき点は何かといった問題意識を持って、認知心理学や社会心理学の観点から観察・研究しています。紀ノ定准教授にとって、今、最も注目しているのが、自動運転へと大きく変わっていく交通環境と人との関係です。
情報デザイン学科の紀ノ定保礼講師は人の認知に興味を持っています。特に、技術の進歩によって変わっていく環境のなかで、人はきちんと認識し対応できるのか、対応できないのであれば技術や社会にフィードバックすべき点は何かといった問題意識を持って、認知心理学や社会心理学の観点から観察・研究しています。紀ノ定准教授にとって、今、最も注目しているのが、自動運転へと大きく変わっていく交通環境と人との関係です。
衝突被害軽減ブレーキに油断する人
運転支援のなかでも多くの新車が標準的に備えるようになってきた機能に「衝突被害軽減ブレーキ」があります。障害物を感知し、衝突の可能性があるときは警報を鳴らす機能です。最近は、衝突の可能性がさらに高くなったときに自動停止する車種が主流となってきました。
「近づいてくる車が衝突被害軽減ブレーキ付きの車種だと認識したとき、人は油断するだろうか」。人の認知と対応を確かめるために、次のような状況を想定しました。場所は交差点。ドライバーが交差点にさしかかろうとしたとき、交差点の右側から侵入しようとする車を発見します。ドライバーには事前に、衝突被害軽減ブレーキ付きの車種だと伝えておきます(実はそれはウソ)。衝突の可能性が出てきたとき、ドライバーは回避するためにブレーキを踏みます。そのタイミングはウソを伝えたときと伝えなかったときで変わるでしょうか、変わらないでしょうか。
「近づいてくる車が衝突被害軽減ブレーキ付きの車種だと認識したとき、人は油断するだろうか」。人の認知と対応を確かめるために、次のような状況を想定しました。場所は交差点。ドライバーが交差点にさしかかろうとしたとき、交差点の右側から侵入しようとする車を発見します。ドライバーには事前に、衝突被害軽減ブレーキ付きの車種だと伝えておきます(実はそれはウソ)。衝突の可能性が出てきたとき、ドライバーは回避するためにブレーキを踏みます。そのタイミングはウソを伝えたときと伝えなかったときで変わるでしょうか、変わらないでしょうか。

実験システムのイメージ。別のシステムで実験の様子を再現してもらった。
実際の実験ではVRゴーグルは使わず、3面のディスプレイを見ながらハンドルとアクセル、ブレーキなどで操作する。
実験はドライビングシミュレーターを使って行いました。運転席から見た外の景色が3面のディスプレイに映し出され、被験者はハンドルとアクセル、ブレーキなどを使って運転状況をシミュレーションします。
経験の浅いドライバーが被験者となったときに興味深い結果が得られました。「衝突被害軽減ブレーキを搭載している」と伝えると、ブレーキを踏むタイミングが遅れるのです。ただ、被験者によって違いがありました。そこでさらに分析すると、衝突被害軽減ブレーキに対する信頼感が高い被験者ほど、ブレーキが遅れることが分かりました。機能に対する信頼は、ともすると過信につながり、それが油断につながるということです。
この結果は、新技術のアピールの仕方に警鐘を鳴らします。「テレビコマーシャルやWebサイト、雑誌などで新技術を伝えるときに、過信を抱かせるような過度なアピールはリスクがあることを示唆する結果です」(紀ノ定准教授)。
経験の浅いドライバーが被験者となったときに興味深い結果が得られました。「衝突被害軽減ブレーキを搭載している」と伝えると、ブレーキを踏むタイミングが遅れるのです。ただ、被験者によって違いがありました。そこでさらに分析すると、衝突被害軽減ブレーキに対する信頼感が高い被験者ほど、ブレーキが遅れることが分かりました。機能に対する信頼は、ともすると過信につながり、それが油断につながるということです。
この結果は、新技術のアピールの仕方に警鐘を鳴らします。「テレビコマーシャルやWebサイト、雑誌などで新技術を伝えるときに、過信を抱かせるような過度なアピールはリスクがあることを示唆する結果です」(紀ノ定准教授)。
見ているだけの運転も長距離は疲れる
運転支援システムというと、前走車に追従して走行するACC(Adaptive Cruise Control)を思い浮かべる人は多いでしょう。高速道路を走行しているときに、アクセルやブレーキを踏まなくても前の車に自動追従できるので、ドライバーの負担を大きく減らせるといわれている機能です。前述の衝突被害軽減ブレーキはなかなか経験できませんが、ACCは利用した人も多いでしょう。
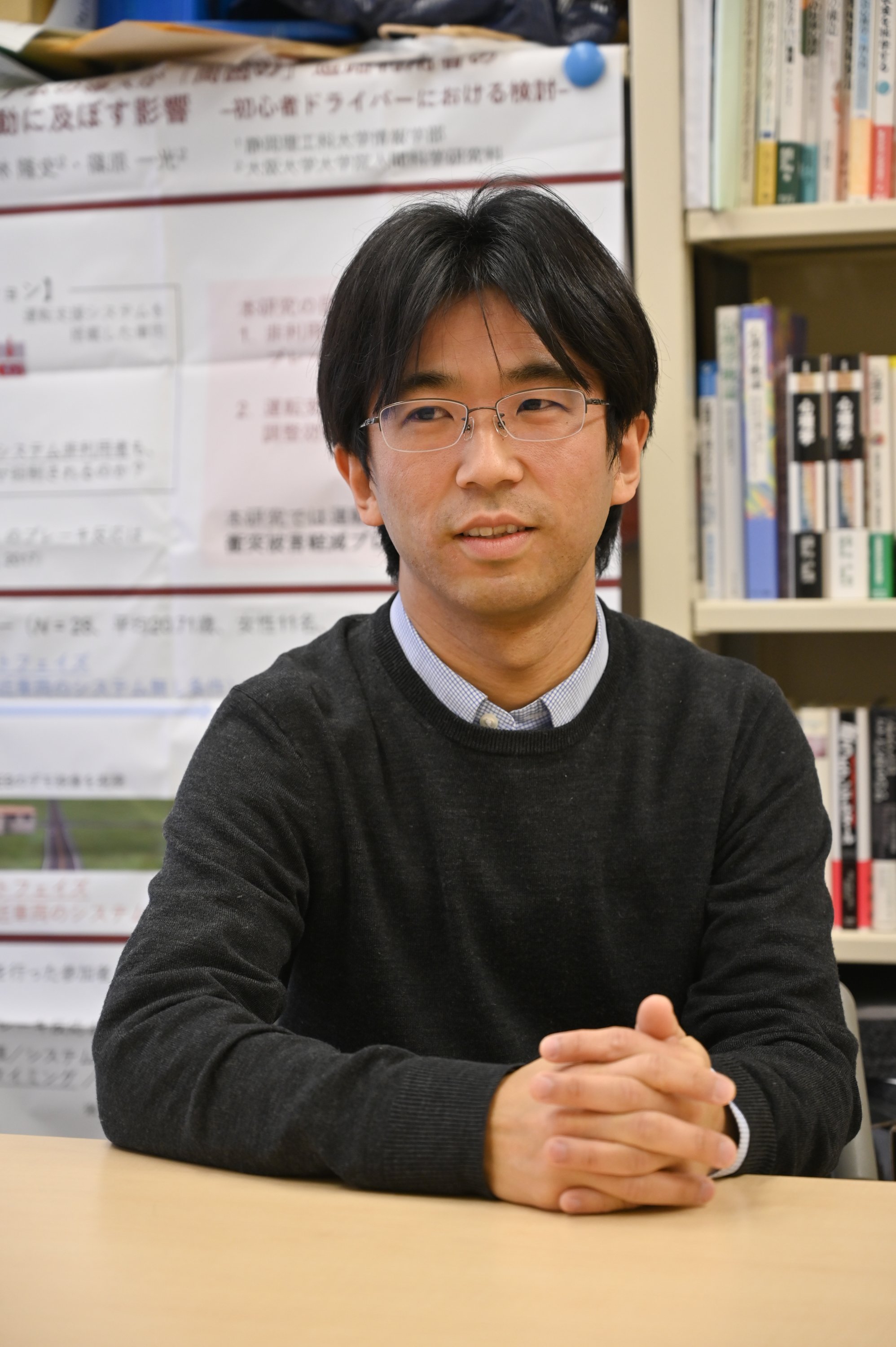
ですが、この「負担を大きく減らせる」という効果も慎重に評価する必要があるといいます。「これは海外の研究者の報告ですが、たとえACC搭載車であっても、長時間運転すると注意力が低下すると指摘しています」。車間距離の心配がなくなり、足の負担も減り、ほぼ周囲の状況を監視するだけの運転であっても、長距離運転では適度な休憩が必要になるということのようです。
完全な自動運転の世界になれば別ですが、今はそこへの移行期です。機械とドライバーという二つの制御主体があるので、周囲もドライバー自身も、車がどういった挙動をするのか、予想がつきにくい面があるのでしょう。
日常の人間をもっと深く知りたいという紀ノ定准教授ですが、一方で、こうした知見が得られても大学では社会実装まで関わることができません。「製品化を考えている企業などと一緒に、知見を製品や社会にフィードバックできたらいいと考えています」(紀ノ定准教授)。
フィードバックが重要になる新技術は車だけではありません。人は今後、いろいろな新技術に晒されることになるでしょう。紀ノ定准教授の活躍の場も広がっていきそうです。
完全な自動運転の世界になれば別ですが、今はそこへの移行期です。機械とドライバーという二つの制御主体があるので、周囲もドライバー自身も、車がどういった挙動をするのか、予想がつきにくい面があるのでしょう。
日常の人間をもっと深く知りたいという紀ノ定准教授ですが、一方で、こうした知見が得られても大学では社会実装まで関わることができません。「製品化を考えている企業などと一緒に、知見を製品や社会にフィードバックできたらいいと考えています」(紀ノ定准教授)。
フィードバックが重要になる新技術は車だけではありません。人は今後、いろいろな新技術に晒されることになるでしょう。紀ノ定准教授の活躍の場も広がっていきそうです。
研究者プロフィール
紀ノ定保礼 准教授
情報デザイン学科
2009年 同志社大学 文化情報学部 文化情報学科卒
2014年 大阪大学大学院 人間科学研究科 博士後期課程修了
2014年 大阪大学大学院 人間科学研究科 助教
2017年 現職
情報デザイン学科
2009年 同志社大学 文化情報学部 文化情報学科卒
2014年 大阪大学大学院 人間科学研究科 博士後期課程修了
2014年 大阪大学大学院 人間科学研究科 助教
2017年 現職

