老化原因「糖化」を抑える食品を探す
物質生命科学科
髙部稚子 准教授
髙部稚子 准教授
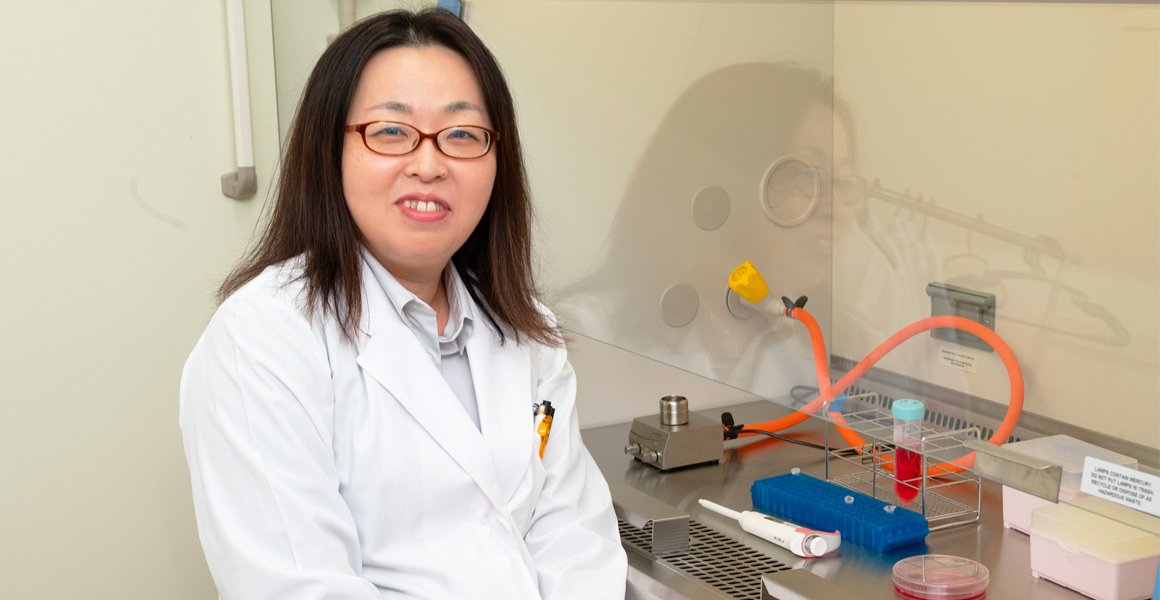
「糖化」が美容と健康の大敵として問題視されています。糖化は体の中で余分な糖がたんぱく質に結びつくことです。最終的には糖化最終生成物(AGEs:Advanced Glycation Endproducts)という名の複数の物質を生成し、体にさまざまな悪影響を与えます。
美容面での影響は肌や髪に出ます。肌のハリを保つコラーゲンたんぱくに糖化が起きると肌の弾力が失われます。髪のたんぱく質が糖化するとハリやツヤがなくなります。皮膚の細胞にAGEsが沈着するとシミやくすみとなります。
健康面では、血管組織の糖化が進むことで動脈硬化のリスクが高まります。動脈硬化が進行すると心筋梗塞や脳梗塞などの心配も出てきます。腎臓にある血液をろ過する膜が糖化によって機能を失うと血液中のたんぱく質が尿に漏れ出し、尿たんぱくの症状が出てしまいます。このほか、骨粗しょう症、ドライアイ、白内障、網膜症なども糖化が引き起こしているといわれています。AGEsはアルツハイマー病との関連も指摘されています。
総じて糖化が体に与えるストレスを糖化ストレスといいます。糖化ストレスは老けを加速させ疾病の原因を作ります。
まさに老化の大きな原因なのです。AGEsが年齢を意味するageと同じスペルになっていることは偶然ではないでしょう。2020年4月に本学に着任した髙部稚子准教授は、糖化ストレスを防ぐ方法を見つけようとしています。
美容面での影響は肌や髪に出ます。肌のハリを保つコラーゲンたんぱくに糖化が起きると肌の弾力が失われます。髪のたんぱく質が糖化するとハリやツヤがなくなります。皮膚の細胞にAGEsが沈着するとシミやくすみとなります。
健康面では、血管組織の糖化が進むことで動脈硬化のリスクが高まります。動脈硬化が進行すると心筋梗塞や脳梗塞などの心配も出てきます。腎臓にある血液をろ過する膜が糖化によって機能を失うと血液中のたんぱく質が尿に漏れ出し、尿たんぱくの症状が出てしまいます。このほか、骨粗しょう症、ドライアイ、白内障、網膜症なども糖化が引き起こしているといわれています。AGEsはアルツハイマー病との関連も指摘されています。
総じて糖化が体に与えるストレスを糖化ストレスといいます。糖化ストレスは老けを加速させ疾病の原因を作ります。
まさに老化の大きな原因なのです。AGEsが年齢を意味するageと同じスペルになっていることは偶然ではないでしょう。2020年4月に本学に着任した髙部稚子准教授は、糖化ストレスを防ぐ方法を見つけようとしています。
糖化を抑える効果、静岡になじみのあの食品は?
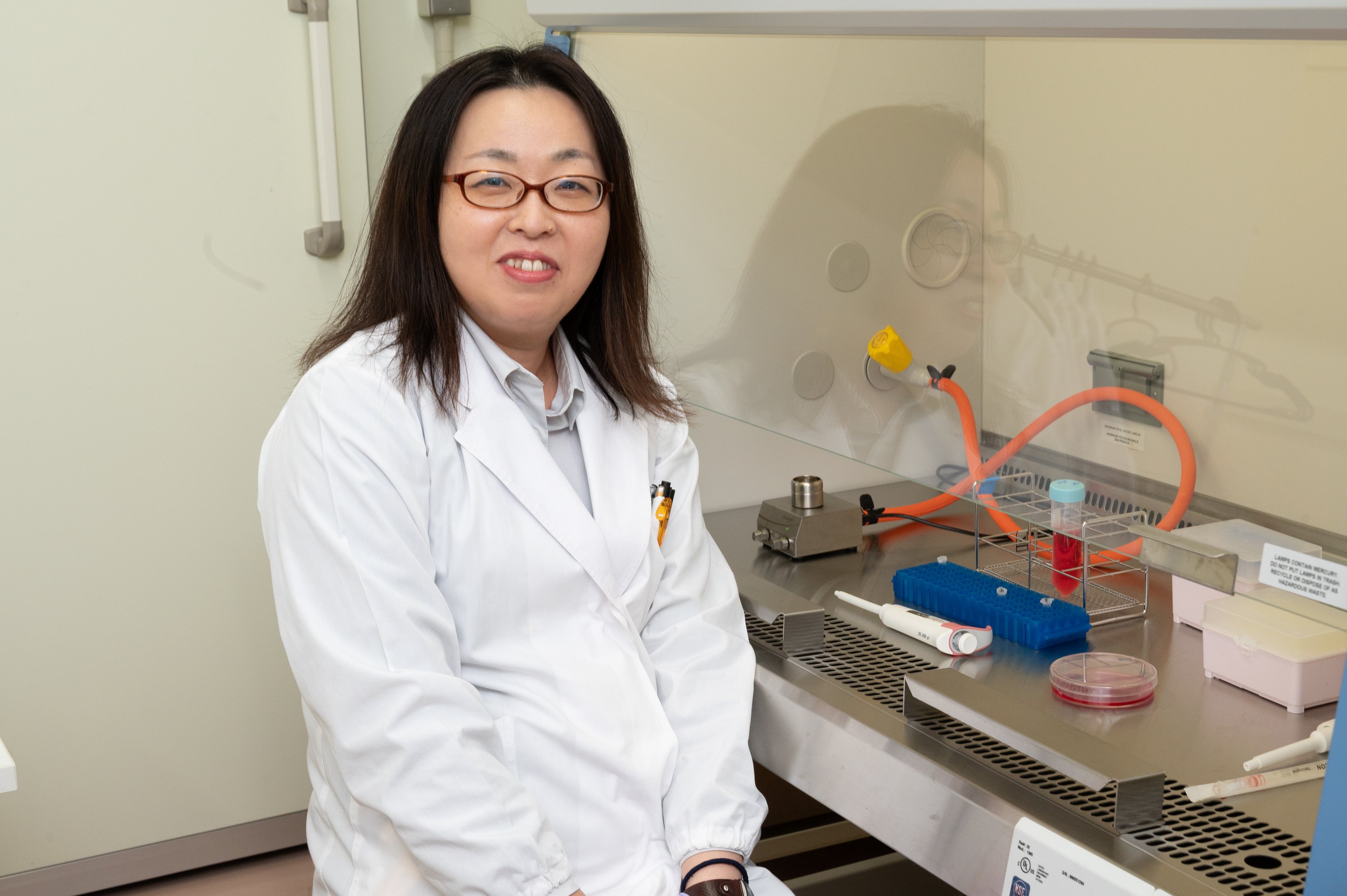
糖化を抑えるにはいくつかのアプローチがあります。よく知られているのは食後に上がる血糖値を抑えること。AGEsが出来やすいのは血糖値が上がる食後30分から1時間なので、この血糖値のピークを押さえ込むことが有効です。「ベジタブルファースト」のように、ご飯より副菜を先に食べることは血糖値のピークを下げる効果があります。食後30分から1時間に軽い運動をすることもピークを下げるには有効な方法です。
また、糖化を抑える植物素材を食べる方法もあります。きのこやブロッコリー、緑茶などで効果が認められていますが、それぞれに効果を発揮する成分は異なります。髙部准教授は、どの食品のどの成分がどのように効果を発揮するのかを詳しく知り、糖化ストレスを防ぐ効果的な方法にたどり着きたいと思っています。
研究室に配属された学生に「調べたい素材はある?」とあえて聞いてみました。学生には興味を持って研究に取り組んでほしいと常々、思っていたからです。すると「お茶」「柑橘類」「いちご」と、静岡県になじみのある素材が挙がりました。
また、糖化を抑える植物素材を食べる方法もあります。きのこやブロッコリー、緑茶などで効果が認められていますが、それぞれに効果を発揮する成分は異なります。髙部准教授は、どの食品のどの成分がどのように効果を発揮するのかを詳しく知り、糖化ストレスを防ぐ効果的な方法にたどり着きたいと思っています。
研究室に配属された学生に「調べたい素材はある?」とあえて聞いてみました。学生には興味を持って研究に取り組んでほしいと常々、思っていたからです。すると「お茶」「柑橘類」「いちご」と、静岡県になじみのある素材が挙がりました。
実は、髙部准教授が前に所属していた同志社大学では500種類以上の食品素材について既に実験を済ませていて、学生たちが挙げた素材についてもある程度の抗糖化作用があることは分かっていました。ですが同じ素材でも人の手が加わることで成分は変わります。髙部准教授はそこに着目しました。
例えば同じ茶の木を原料にしたお茶でも葉をどこまで発酵させるか、どう蒸すかによって糖化を抑える作用が変わる可能性があります。そこで緑茶から数種類、ウーロン茶から数種類を評価し、有効成分や効果がどう変わったのか調べることにしました(※)。いちごでは栽培法の違いに着目しました。異なる栽培法で育てたいちごで、成分や効果に差がでるのかを調べます。
※抗糖化作用の評価方法:たんぱくと還元糖を含むリン酸緩衝液中に食品素材の抽出物を添加して反応させ、生成されたAGEs や糖化反応中間体の量を測定する
加工方法や栽培方法によって効果に差が出ることが分かれば、糖化を気にしている人にはより効果のある食材を薦めることができます。また、食品を生産する人たちには、より多くの抗糖化成分が出来る加工法や栽培方法を知らせることができます。出荷の際にそうした方法を採用していることをアピールすることもできるでしょう。
例えば同じ茶の木を原料にしたお茶でも葉をどこまで発酵させるか、どう蒸すかによって糖化を抑える作用が変わる可能性があります。そこで緑茶から数種類、ウーロン茶から数種類を評価し、有効成分や効果がどう変わったのか調べることにしました(※)。いちごでは栽培法の違いに着目しました。異なる栽培法で育てたいちごで、成分や効果に差がでるのかを調べます。
※抗糖化作用の評価方法:たんぱくと還元糖を含むリン酸緩衝液中に食品素材の抽出物を添加して反応させ、生成されたAGEs や糖化反応中間体の量を測定する
加工方法や栽培方法によって効果に差が出ることが分かれば、糖化を気にしている人にはより効果のある食材を薦めることができます。また、食品を生産する人たちには、より多くの抗糖化成分が出来る加工法や栽培方法を知らせることができます。出荷の際にそうした方法を採用していることをアピールすることもできるでしょう。
発酵食品の課題と期待
発酵食品は人が手を加えた食品といっていいでしょう。味噌や納豆、それにチーズも発酵食品です。
発酵食品は概ね高い抗糖化効果が認められます。例えば八丁味噌の発酵・熟成過程で発見された「発酵イソフラボン」は抗糖化成分として有名です。
「でも、発酵食品は一筋縄ではいかないのですよ」と髙部准教授は言います。以前、ある発酵食品に取り組んだときに測定値が大きくぶれたことがあったそうです。原因はロットの違いでした。
食品メーカーは気温や原材料などがロットごとに違っても、味や風味を一定の水準以上にするよう発酵過程を管理します。食品成分表にも大きな違いはありません。ですがやはり成分にばらつきはあるのです。発酵は微生物の営みです。品質として気にしていた部分ではない部分で違いが出る可能性もあります。
これは食品メーカーにとって、今まで見逃していたチャンスかもしれません。これまで気にしていなかった抗糖化に注目しながら成分や発酵過程をコントロールすることで、より抗糖化作用の高い食品を提供できる可能性があるということです。
食品メーカーの協力が欠かせない取り組みではありますが、髙部准教授との共同研究に発展したならばどうでしょう。抗糖化効果の高い新たな商品が生み出され、糖化に悩む人たちの選択肢が増えることになるかもしれません。想像に期待が膨らみます。
発酵食品は概ね高い抗糖化効果が認められます。例えば八丁味噌の発酵・熟成過程で発見された「発酵イソフラボン」は抗糖化成分として有名です。
「でも、発酵食品は一筋縄ではいかないのですよ」と髙部准教授は言います。以前、ある発酵食品に取り組んだときに測定値が大きくぶれたことがあったそうです。原因はロットの違いでした。
食品メーカーは気温や原材料などがロットごとに違っても、味や風味を一定の水準以上にするよう発酵過程を管理します。食品成分表にも大きな違いはありません。ですがやはり成分にばらつきはあるのです。発酵は微生物の営みです。品質として気にしていた部分ではない部分で違いが出る可能性もあります。
これは食品メーカーにとって、今まで見逃していたチャンスかもしれません。これまで気にしていなかった抗糖化に注目しながら成分や発酵過程をコントロールすることで、より抗糖化作用の高い食品を提供できる可能性があるということです。
食品メーカーの協力が欠かせない取り組みではありますが、髙部准教授との共同研究に発展したならばどうでしょう。抗糖化効果の高い新たな商品が生み出され、糖化に悩む人たちの選択肢が増えることになるかもしれません。想像に期待が膨らみます。
研究者プロフィール
髙部稚子 准教授
物質生命科学科
1997年 東京理科大学 工学部 工業化学科卒業
2000年 東京大学大学院 工学系研究科 博士課程修了
2002年 株式会社島津製作所
2003年 中外製薬株式会社
2006年 東京大学大学院 工学系研究科 特任助教
2007年 南カリフォルニア大学 工学部 研究員
2010年 エモリー大学 医学部 研究員
2013年 同志社大学 生命医科学部 特任助教
2015年 同志社大学 生命医科学部 チェア・プロフェッサー准教授
2020年 現職
物質生命科学科
1997年 東京理科大学 工学部 工業化学科卒業
2000年 東京大学大学院 工学系研究科 博士課程修了
2002年 株式会社島津製作所
2003年 中外製薬株式会社
2006年 東京大学大学院 工学系研究科 特任助教
2007年 南カリフォルニア大学 工学部 研究員
2010年 エモリー大学 医学部 研究員
2013年 同志社大学 生命医科学部 特任助教
2015年 同志社大学 生命医科学部 チェア・プロフェッサー准教授
2020年 現職

